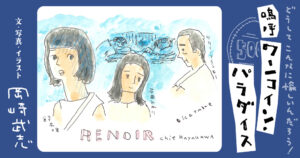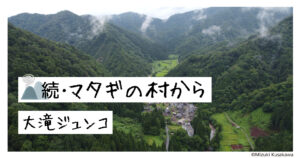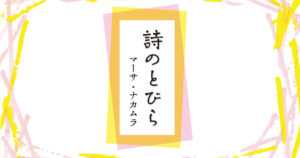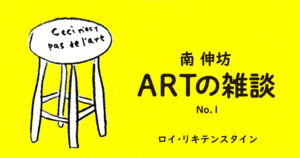第12回 なにかいいことあるの?
三年生になって、娘は毎日学校に行くようになった。
ただし、一日一コマだけで、その四十五分の授業にも毎回五分か十分くらい遅れて参加するので、小学校に滞在するのはだいたい三十分程度だ。
授業が終わると、家の近くのファミリーマートに立ち寄って、昼食におにぎりと野菜スティックを買ったり、おやつを買ったりする。
「今日もよくがんばったね」
ぼくがいうと、娘は笑顔でうなずくのだが、その顔が「ああ、学校が終わって私はほんとうにうれしい」という顔なので、ぼくは毎回複雑な気持ちになる。
幼いころはどちらかというと、手のかからない子だった。座るのも、立つのも、しゃべるのも、絵本を読むのも、まわりの子どもたちよりすこし早く、こちらが手取り足取り教えなくても、たいていのことはひとりでできた。
ひとを笑わせるのも得意だった。なにかの真似をしたり、身体全体をつかってふざけたりするというのではなく、相手の顔色を見て、ここぞというタイミングでおもしろいことをいった。ぼくは幼い娘のそうした面にふれるたび、この子はかしこいから、早く巣立っていってしまうのだろうなあ、と思っていた。
他の子とすこし様子がちがうな、と感じたのは、幼稚園に入ってからだ。家ではよくしゃべり、喜怒哀楽も豊かだったが、園服を着て家を離れると、彼女の顔から表情が消え、口から言葉が消えた。
最初のうちは親から離れるのがつらいからだろう、と思っていたが、結局、卒園するまでの二年間、そのことは変わらなかった。
忘れられないのは、娘が幼稚園で撮ってもらったという、お面にできるくらいに大きな彼女の顔写真を見たときのことだ。
そこには、表情というものがまったくなかった。娘は、生まれてすぐに両親から見放され、愛情というものを一切知らずに育ったというような顔で写真に写り、まっすぐにこちらを見つめていた。
参加する授業はいつも前日に決めた。娘はとにかく「勉強がたいへんじゃないやつを」と主張したが、今後のことを考えると、算数の授業だけはなるべく回避したくなかった。
三年生ぐらいのレベルであれば、国語も、社会も、理科も、道徳も、娘のそれまでの人生経験と、その日に習う知識で対応することができた。
が、算数だけはそうではなかった。グラフや時間の計算ぐらいならまだしも、「割り算のあまり」を求めるというところにまでいくと、実生活の知恵だけでは解くことは難しかった。
算数の授業は毎日あった。一時間目に算数があるときはいっしょに朝食を食べ、ふたりで手をつないで学校へ向かった。二時間目、三時間目、四時間目のときは、ぼくは近所のコーヒーチェーン店で一時間ほど仕事をしてから娘と学校へ行った。
たいへんなのは五時間目に算数の授業が組まれているときだった。
その日はふだんより早起きして七時半に家を出て、三十五分自転車をこいで吉祥寺の事務所へ行き、そこで三時間ほど仕事をしてから娘の授業に付き添った。そして、授業が終わるとまた自転車で事務所に向かい、二時間ほど仕事をした。
「今日はなにかいいことある?」
娘は決まって、ぼくに聞いた。
ぼくはその問いにたいして、ずいぶんと長いあいだ、「人生はそんなに楽しいことばかりじゃないよ。楽しくないことも多いから、だから、とくべつなことがあると、すごくうれしいんだよ」とこたえていた。
でも、娘は何回聞いてもそのこたえに納得できないようで、同じクジを毎日引いていたらいつか大当たりが出るだろう、というように、朝が来るたびぼくに、「今日はなにかいいことある?」とたずねた。
機嫌がわるい日は、「そんなのないよ」と冷たくこたえたりもした。が、そのうち、ぼくのほうで、娘に毎日「なにかいいこと」をプレゼントしたい気持ちになってきた。
四月のある日、ふと思いついて「じゃあさ、学校に行く前とか行ったあとに、毎日パパとSwitchやらない?」と提案した。
ぼくはこれまで、子どもたちのSwitchにほとんど触れてこなかった。
それは昔のめり込んでいたテレビゲームに再び触れることで仕事に差し障りが出ることをおそれていたからであるが、いま考えてみると、それよりもたんじゅんに、加齢のために新しいなにかをやるということにたいして億劫になっていからであった。
「パパ、ゲームやるの?」
娘はうれしそうな顔でいった。
ぼくがうなずくと、娘は漫画のなかの子どもがいうみたいに、大きな声で
「やったー!」
といった。
(続く)

しまだ・じゅんいちろう 1976年、高知県生まれ。東京育ち。日本大学商学部会計学科卒業。アルバイトや派遣社員をしながらヨーロッパとアフリカを旅する。小説家を目指していたが挫折。2009年9月、夏葉社起業。著書に『父と子の絆』(アルテスパブリッシング)、『長い読書』(みすず書房)などがある。
バックナンバー